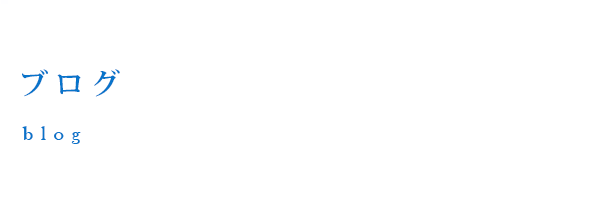(前回までのメルマガは こちらから ご覧ください)
「マインドフルネスを練習する時間なんてありません。」「瞑想はしたいけど、ついやるのを忘れてしまいます。」 「瞑想は難しいです。私の心はいつもとりとめなくフラフラ
してしまうんです。」
以上が、私のマインドフルネスプログラムの参加者が最もよく口にする3つの障害です。
ここではあえて「障害」と表現します。なぜなら、これがあなたとご自身のマインドフルネスの実践との間に現れる障害物だからです。
しかしこれは克服することができます。 実は「人格の強み」が瞑想の実践に大きなエネルギーを与えてくれるのです。
一つ目の方法は、自分自身の一番強い内的性質に意識を向けることです。この方法は、障害から学び、瞑想の実践に打ち込むのにはベストな方法の一つです。
では、障害を克服するために、最高の人格の強み(いわゆる、いちばんの強み)をどう活用すればよいでしょう?
MBSPプログラムの中で、私はこれを「強いマインドフルネスを育む」と呼んでいます。
これはマインドフルネスの実践の助けとして、自身の人格の強みを活用することを指しています。
これを3つのステップで行っていきます。
ステップ2では、24のポジティブな人格を瞑想に集中するためどう役立てるか、その実例をご紹介しています。
そこに挙げられていることで、例えば呼吸瞑想、歩行瞑想といったものは、ほとんどのマインドフルネスの実践に応用することができます。
ステップ1:
あなたのいちばんの強みを1つ選んでください。
ステップ2:
下記のいずれから、あなたの強みに一番ぴったりくるものを見つけてください。
「創造性」
座る姿勢や呼吸との間合いの取り方をいろいろ変えてみたり、心がさまようのを制御するため、何か別の方法で実践してみる。
「好奇心」
今この瞬間にどんなことが頭に浮かんでは消えるか、それを探るのを決して止めないこと。
「判断・批判的思考」
呼吸に戻る前の数秒の間にあなたの心の中でわき上がる雑念を吟味してみる。
「学習欲」
マインドフルネスと瞑想的読書を融合させてみる。
「大局観」
哲学的な本を読むことをマインドフルネスを融合させてみる。
「勇気」
自分自身に挑戦し続けること! 身体の位置(例えば、座る方法、脚を交差させる方法など)を緩やかに変化をつけて挑戦してみたり、呼吸とともに筋肉を緊張させたり、内側の不快感に向かい合ったり、練習環境を変えて行ってみるなどの挑戦をしてみましょう(例えば、違う天気の下で行うとか、うるさい環境や静かな環境などで行ってみるなど)。
「忍耐力」
各瞑想セッションの開始時に、心が落ち着かない、音や体が緊張してしまう、といったあらゆる障害を克服しようと自分に喝を与え、挑戦を課してみる。
「誠実さ」
自分自身について、これまで見えてなかったことに少なくとも1つ気づくようにし、自らをよりはっきりと見つめる機会として、各瞑想体験を捉えてみる。
「熱意」
座位の瞑想と、マインドフルネス歩行を融合させる(座っては歩き、また座る、を繰り返すなど)。
「愛」
今生きている人、すでに亡くなっている人を問わず、瞑想を通じて、その人に愛のこもった思いをささげるのだと考え、瞑想を実践してみる。その時、毎回違う人を選ぶように心配りをすること。
「親切心」
瞑想を実践に、思いやりの実践(自分への思いやり、他人に対する思いやり)を毎回組み込んでみる。
「社会的知性」
瞑想する間は、毎回苦しみを抱えている人たちのことを思い浮かべ、その人たちに心を寄せてみるようにする。
「チームワーク」
だれかと一緒に、または瞑想グループやスピリチュアルなコミュニティーの中で、瞑想を実践してみる。
「公平性」
瞑想を行う間、地球上の 「生きとし生けるものすべて」(人間、動物、植物、およびその他の生物を含む)に対して、恵みを与えることを意識して実践してみる。
「リーダーシップ」
新たに瞑想を行う時は、その準備として、これから行っていきたいことを段階に分け組織化してみる。
「許し」
各瞑想の前に、意図的に「手放し」を行ってみる。息を吐きながら緊張を緩め、ストレスやとがめ、心の鎧といったものを手放していくこと。
「謙虚さ」
瞑想を始めるときに、生命の有限さについて改めて考えてみる。あなた自身、そしてあなたの愛する人たちすべてが、やがては死すべき存在だということを思い起こしてみるのです。
「慎重さ」
姿勢や、呼吸の流れ、手の配置など、基準となる指示にきちんと従って瞑想を行ってみる。
「自己調整」
1週間、同じ日、同じ時間、同じ時間の量、同じ練習というように規則正しい日課を組み立て、それに従いましょう。
「審美眼」
野外で座りながらのマインドフルネスを行ったり、マインドフルネス歩行の実践に取り組んでみる。そのときは、目をしっかり開いていること。
「感謝」
瞑想の始めと終わりに、感謝の念を吹き込んでみる。
「希望」
一日の中で、自分のエネルギーが一番高い時に瞑想を行う。それから楽観的な言葉で締めくくること。
「ユーモア」
各瞑想の前日にあった面白くて有意義な会話、経験を心の中で再現してみる。
「スピリチュアリティー・宗教性」
瞑想の始めと終わりに、祈りを込めてみる。または瞑想と「センターリングの祈り」(キリスト教の中で、神と近づくために行う瞑想法)とを融合させてみる。
ステップ3
次回瞑想を行う際は、自身のいちばんの強みを瞑想の中に組み込んでみてください。
心や身体に、何か邪魔が入ったなと感じたときは、自然と活性化している自分のいちばん顕著な強みを使ってそれを制御します。
必要に応じて、2番目に顕著な強みも発揮してみてください。
ステップ2のエクササイズとその考え方は、瞑想の実践にパワーと情熱が与えるよう構成しています。
おそらくみなさんも、高いレベルでモチベーションを感じるとき、ご自身のいちばんの強みが関係したところでそれを感じるのではないでしょうか。
そうであれば、その強みを瞑想に活かさない手はありません。瞑想への障害を乗り越え、もう一度瞑想を行いたいと感じることで、瞑想の実践がもっと定着するようになります。
以上の方法で、瞑想を「やらなきゃ」という気持ちから行うのではなく、瞑想実践自体を目的とした(すなわち、本質的に動機づけられる)ものになっていくのです。